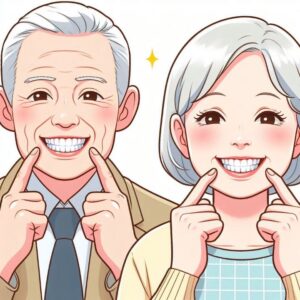皆さん、予防歯科をしていますか?
「予防歯科」という言葉、聞いたことはあっても、
「なんだかお金がかかりそう…」
「別に、今、歯が痛くないから大丈夫」
そう思っている方も多いのではないでしょうか?
実は、私もそうでした。
昨年までは、私も予防歯科には縁がなく、歯が痛くなったら歯医者さんに行く、という感じでした。
しかし、昨年歯の治療に行ったのをきっかけに予防歯科を始め、それを機に改めて予防歯科について調べてみて、
「もっと早くやっておけばよかった!」 と心から思いました。
なぜなら、予防歯科は、将来の医療費を大幅に削減できる可能性があるからなんです!
今回は、予防歯科の重要性と利点について、皆さんにお伝えしたいと思います。
読み終わった後には、きっとあなたも予防歯科を始めたくなるはずです!
予防歯科との出会い
FIRE生活を始めてから、初めてアポイントのある外出をしてきました。時間に縛られない生活に慣れていたため、気づけば予定していた出発時間を過ぎてしまい、急ぎ足で向かうことに。目的は、歯医者での定期検診とクリーニングです。
予防歯科には以前から興味がありましたが、「費用がかかる」「面倒くさい」という思いから、長らく放置していました。しかし昨年、詰め物が取れたのをきっかけに治療へ行き、そこから定期的なメンテナンスを始めることにしました。今では、定期検診とクリーニングを習慣にしています。
クリーニングの体験とその効果
クリーニングでは、歯の表面や歯間、歯周ポケットを徹底的に掃除します。悪くなっている部分の歯周ポケットを掃除すると、痛みを伴うこともあり、うがいをすると血が混じることも。ですが、その分「しっかりケアできている」と実感できました。
自宅で鏡を見てみると、落ちにくかった着色汚れがすっきりし、フロスの通りも良くなりました。定期的に受けることで、口腔環境が明らかに改善されるのを感じています。
虫歯と歯周病の患者数の推移とその理由
ところで現在日本では、虫歯の患者数は減少傾向にある一方で、歯周病の患者数は増加傾向にあります。厚生労働省の調査によると、特に小児や若年層においては、虫歯のない人の割合が増加しており、2022年の調査では9歳以下の虫歯有病率はわずか2.5%にとどまっています。これは、フッ素塗布の普及や学校での歯科検診、保護者の意識向上が要因と考えられています。
一方、歯周病の有病率は依然として高く、特に40代以降で顕著です。歯周ポケットが4mm以上ある人の割合は、65~74歳で56.2%、75歳以上では56.0%に達しており、加齢とともに増加する傾向にあります。また、歯を失う原因の約66%が歯周病によるものとされており、放置すると歯の喪失につながるリスクが高まるため、早期からの予防が重要です。
歯周病増加の背景と予防の重要性
虫歯が減少し、歯周病が増加している背景には、以下のような要因が考えられます。
- 食生活の変化: 柔らかい食べ物や加工食品の摂取が増え、噛む回数が減ったことで、歯茎が弱くなる傾向があります。
- 生活習慣の変化: 忙しい現代人の生活習慣の乱れ(睡眠不足、ストレス、運動不足など)が、免疫力の低下を招き、歯周病を進行させる可能性があります。
- 高齢化社会: 日本の高齢化が進み、歯周病罹患率の高い高齢者の割合が増加しています。
- 歯磨き習慣の変化: フッ素入り歯磨き粉の使用により虫歯は予防できても、歯周病の原因菌である歯周病菌に対する効果は限定的です。私感ですが、若い人達がフッ素入り歯磨き粉の普及などで虫歯治療経験のないことが、かえって正しい歯磨きの重要性を忘れさせてしまって、歯周病患者数はこの先も増加していくのではないかなと思うところがあります。
このような背景から、歯周病予防の重要性はますます高まっています。歯周病は、初期には自覚症状がないため、気づいたときには進行しているケースが多く見られます。定期的な歯科検診とクリーニング、正しい歯磨きとフロスの使用、食生活の改善など、予防歯科の取り組みが重要となります。
予防歯科とは?
予防歯科は、虫歯や歯周病を未然に防ぐことを目的とした歯科医療です。具体的には、
- 定期検診とクリーニング
- フッ素塗布
- 正しい歯磨きやフロスの習慣化
- 食生活の見直し
といったケアが含まれます。
予防歯科の具体的な取り組み
定期検診とクリーニング
定期的な検診とクリーニングは、虫歯や歯周病の早期発見・早期治療に効果的です。歯科医師や歯科衛生士によるプロのクリーニングは、自宅での歯磨きでは取り切れないプラークや歯石を取り除くことができます。特に、歯周病の予防にはクリーニングが欠かせません。
フッ素塗布
フッ素は歯のエナメル質を強化し、虫歯を予防する効果があります。歯科医院で定期的にフッ素塗布を受けることで、虫歯のリスクを大幅に減らすことができます。
正しい歯磨きとフロスの習慣化
予防歯科の基本は、毎日の正しい歯磨きとフロスの使用です。歯科医師や歯科衛生士から正しい歯磨きの方法を教わり、それを実践することで、口腔内の健康を維持できます。特にフロスは、歯と歯の間に詰まった食べ物やプラークを取り除くのに効果的です。
食生活の見直し
バランスの取れた食事は、歯と歯茎の健康にとって重要です。特に、糖分を多く含む食品や飲料は虫歯の原因となるため、控えるよう心がけましょう。また、カルシウムやビタミンDを含む食品を摂取することで、歯の強化に役立ちます。

歯周病が引き起こす全身の病気
歯周病は口の中だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼします。例えば、
- 心疾患:歯周病菌が血流に入り込み、心筋梗塞や心不全のリスクを高める。
- 糖尿病:歯周病がインスリンの働きを妨げ、糖尿病を悪化させる。
- 脳血管障害:歯周病菌が脳へ到達し、脳梗塞のリスクを増加させる。
- 誤嚥性肺炎:高齢者の肺炎の原因となることがある。
- 認知症:慢性的な炎症が脳の健康に悪影響を及ぼす。
- メタボリックシンドローム:炎症がインスリン抵抗性を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高める。
このように、予防歯科は単に歯を守るだけでなく、全身の健康を維持し、結果的に医療費を抑える効果があるのです。
日本人の生涯医療費と予防の重要性
日本人の生涯医療費は、一人当たり約2,700万円といわれています。そのうち高齢期(70歳以降)にかかる医療費は約1,700万円と、全体の6割以上を占めます。特に歯周病や生活習慣病の治療費が大きな割合を占めており、若いうちから予防することで医療費の大幅な削減が可能です。
予防歯科は医療費を削減できるのか?
「定期的に通うと費用がかかる」と思われがちですが、長期的には大幅な節約につながります。
予防歯科の経済的メリット
「定期的な歯科検診やクリーニングは費用がかかる」と考えがちですが、実際には長期的に見ると大幅な医療費削減につながります。具体的なデータを用いて、その効果を説明します。
予防歯科にかかる年間費用と治療費の比較
予防歯科にかかる年間費用は以下の通りです(日本の一般的な費用水準)。
| 項目 | 費用 (年間) |
|---|---|
| 定期検診 (年2回) | 6,000円~10,000円 |
| クリーニング (年2回) | 8,000円~15,000円 |
| フッ素塗布 (年2回) | 4,000円~6,000円 |
| 合計 | 18,000円~31,000円 |
これに対し、虫歯や歯周病が悪化した場合の治療費は次のようになります。
| 治療内容 | 費用 (1本あたり) |
| 虫歯の初期治療 (小さな詰め物) | 5,000円~10,000円 |
| 虫歯の進行治療 (大きな詰め物やクラウン) | 20,000円~50,000円 |
| 根管治療 (神経を取る治療) | 30,000円~100,000円 |
| インプラント治療 (歯を失った場合) | 300,000円~500,000円 |
| 合計 | 数万円~数百万円 |
例えば、定期的に予防歯科を受けていれば、歯を失うリスクが大幅に低減し、インプラントなどの高額な治療を回避できます。
予防歯科がもたらす医療費削減のデータ
厚生労働省や日本歯科医師会の調査によると、定期的に歯科検診を受けている人とそうでない人の生涯医療費には以下のような違いがあります。
- 歯科検診を受けている人の生涯歯科医療費は約 100万円
- 歯科検診を受けていない人の生涯歯科医療費は約 200万円~300万円
また、ある調査によると、定期的に予防歯科を受けている人の医療費は、受けていない人に比べて30~40%低いことが報告されています。
歯周病と全身疾患の関係による追加の医療費削減
歯周病は単なる口腔の問題にとどまらず、全身の健康にも大きな影響を及ぼします。具体的には、以下の疾患との関連が指摘されています。
心血管疾患と歯周病の関係
歯周病菌が血流に入り込むことで動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まります。米国心臓協会(AHA)の研究によると、歯周病の人は心血管疾患を発症するリスクが1.5~2倍になるとされています。
これに伴い、心筋梗塞や脳梗塞の治療費が発生します。
| 疾患 | 平均治療費 |
| 心筋梗塞 | 300万円~500万円 |
| 脳梗塞 | 200万円~600万円 |
予防歯科を徹底することで、こうした高額な医療費を回避できる可能性があります。
糖尿病との関連
歯周病と糖尿病には相互関係があり、歯周病を治療することで糖尿病の管理が改善されることが分かっています。日本糖尿病学会の報告によると、歯周病の治療を行うことで、糖尿病の治療費が年間約10万円削減できるとされています。
高齢期の医療費削減と生活の質の向上
日本人の生涯医療費は一人あたり約 2,700万円 であり、そのうち 高齢期(70歳以降)にかかる医療費は約1,700万円(全体の63%) を占めます。この高齢期の医療費の中で、口腔の健康が大きく影響するものには次のようなものがあります。
- 誤嚥性肺炎(年間の医療費 50万円~100万円)
- 認知症リスクの低減(介護費用 1,000万円以上の削減可能)
- 骨折・転倒リスクの低減(入院費 50万円~200万円削減)
特に、歯が少ないと食事が不十分になり、栄養状態が悪化し、身体機能の低下を招きます。健康な歯を維持することで、高齢期の医療費削減につながるのです。
予防歯科は長期的なコスト削減につながる
以上のデータから、予防歯科に定期的に通うことで、以下のような経済的メリットが得られることがわかります。
- 歯科治療費の削減(生涯で100万~200万円の削減)
- 全身疾患の医療費削減(心血管疾患や糖尿病のリスク低減)
- 高齢期の医療費と介護費用の削減(誤嚥性肺炎や認知症の予防)
- QQL(生活の質)の向上(健康な歯を維持することで日常生活の快適さを確保)
予防歯科がもたらすQOL(生活の質)の向上
予防歯科によって次のような日常生活にプラスの影響が出ると思われます。
- 食生活の充実
定期的な予防歯科のケアは、虫歯や歯周病を未然に防ぐことで、口腔内の健康を維持します。自分の歯でしっかりかんで食事ができることで料理の味もしっかり感じることができ、食事を楽しむことができます。
- 痛みや不快感の軽減
虫歯や歯周病が進行すると、痛みや不快感を引き起こします。定期的なクリーニングと検診でこれらを防ぐことで、日常生活の中で痛みに悩まされることがなくなり、快適な生活を送ることができます。
- メンタルヘルスの向上
歯の健康が保たれることで、自信や自己肯定感が向上します。口臭や歯の見た目を気にせずに人と接することができます。また、発音も明瞭になり、人と話す際の自信も向上し、社会的な活動やコミュニケーションが円滑になります。これにより、メンタルヘルスも向上し、ストレスの軽減にもつながります。
- 長寿と高齢期の生活質向上
口腔内の健康が維持されることで、高齢期においても健康な歯を保ち、食べ物をしっかり噛むことができます。これにより、栄養状態が改善され、長寿や高齢期の生活質が向上します。歯の健康が全身の健康と直結していることから、予防歯科は長寿と健康寿命の延伸にも貢献します。
- 美しい笑顔と自信
健康な歯と美しい笑顔は、自信を持って人前に立つことができる要素です。予防歯科のケアによって、歯の白さや整った歯並びを維持することができ、自信を持って笑顔を見せることができます。これにより、社交的な活動や仕事でのパフォーマンスも向上します。
このように、予防歯科は生活の質(QOL)を多方面から向上させる効果があります。
予防歯科は賢い投資
予防歯科は「健康維持」という観点からも、「将来の医療費削減」という点からも、非常に費用対効果が高い投資です。
今はまだ症状がなくても、若いうちから予防を始めることで、将来の医療費を大幅に削減できるだけでなく、健康寿命を延ばすことにもつながります。予防歯科は「費用」ではなく、「未来への賢い投資」として捉えましょう。これからの毎日をより快適に、健康的に過ごすために、予防歯科を始めてみてはいかがでしょうか?